
|
開会式
会長あいさつ
(社)全国青年の家協議会会長 内田忠平
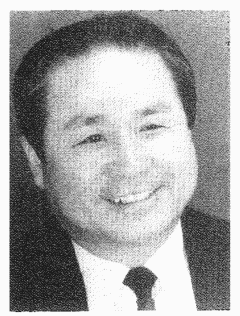
本日は朝早くから、総会に引き続きまして代表者会議を開くことができましたことを大変うれしく思います。日夜、青少年の健全育成のためにご努力いただいております方々が、北海道から沖縄まで一同に会し、今回の代表者会議そして秋の運営研究協議会が開催できますことを、主催者といたしまして厚く御礼申し上げます。
また、この代表者会議のために、公務ご多忙の中、いろいろと愛情を持ってご指導いただいております文部省生涯学習局の草原局長を始め、金森青少年教育課長並びにこの会場を提供いただいております、国立オリンピック記念青少年総合センターの田原所長にもご出席を賜り、この会の有意義な点をご指導いただくことを大変光栄に、また、うれしく思っております。
さて、この全国青年の家協議会は、今から36年前、1960年に31施設をもってスタートいたしました。31の施設でとにかく連携をとって、青年の家の意気を上げようじゃないか、ということで始めたものでございます。その後、1973年、昭和48年3月26日に衣替えをし、社団法人全国青年の家協議会としてスタート、今日に至りました。その間、所長会議であるとか、運営研究協議会の開催、あるいは、青年の家の現状と課題、全国青年の家だよりの発行、また海外派遣事業、地区別事業の助成、施設職員の研修等を行ってまいりました。
青年の家ができました当時は、進学率が51.5%ございましたが、現在は96.7%と非常に多く、対象も変わってきております。そうした中で、新しく青年の家をどう持っていくか、長期的なビジョンを見つめた魅力ある施設、とくに公立青年の家を目指してということで、中央教育審議会の部会長をなさっております河野先生にお入りいただき、外部の方のご意見を聞きながら、公立青年の家の在り方についてただいま議論をしているところでございます。3月と5月に2回ほど会議を持ちました。その中で、各界各層の方が申された意見を幾つかご紹介いたしますと、例えば、時代をしっかりと見つめた夢とロマンのある青年の家をつくったらどうだろうかとか、青年の家は、生命力を動かすスポットになったらどうだろうか。青年の家というものは、地域の生きがいづくりの心の居場所になっているかどうか、こういう点を検討しようじゃないか。また、青年自らが、ソフトづくりやハードづくりに参画してもらうような青年の家をつくったらどうだろうか。と、このような意見が出ております。とにかく、今、現代の若者に必要な体験学習とか生きがいをつくる青年の家を、北海道から沖縄までこの会のネットワークを通して、もう1度盛り上げようじゃないか。というのが外からの常識としての委員会の意見でございました。
そうした外部の意見を踏まえ、私ども内部の常識といいますか、中でどうするかということについて、今日から明日にかけて話し合っていきたいと思います。いわば2日間のドラマでございます。その中にはいろいろなホットなニュースもございます。学社融合という話題になった言葉はいったい何だろうか、もう少し知りたいという要望もありました。これについては、明日、荒谷社会教育官にお話しをしていただくことにしております。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|